
ホーム>学部・学科>アニメーション文化学部 アニメーション文化学科>教員インタビュー アニメーション文化学部で学ぶということ

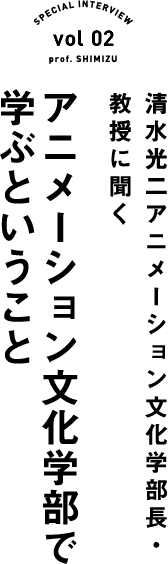
清水光二吉備国際大学アニメーション文化学部長・教授。脚本も手掛けた監督作品「よるべしるべ」のポスターとともに。
1956年生まれ。専攻:ヨーロッパ文学(英文学を除く)、外国語教育。吉備国際大学文化財学部アニメーション文化学科長等を経て、2014年4月から現職。2014年2月、「さぬき映画祭・映像作品企画募集(一般部門)」において、オリジナル・シナリオ「よるべしるべ」が映像化作品に決定。同映画祭の支援を受けて、映画化。2015年2月同作品を「さぬき映画祭2015」で上映し、表彰を受ける。2015年2月第11回順正学園学術交流コンファレンス創立者加計勉賞受賞。

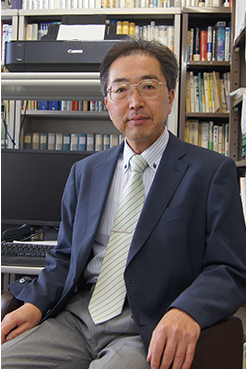
研究室の愛用のノートPCの前で。後ろの本棚には、ドイツ語学・ドイツ文学関連の多数の書籍が見える。
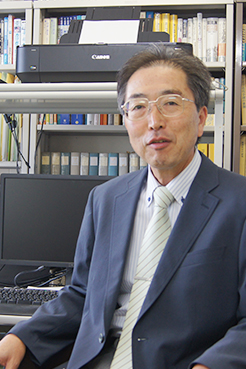


清水先生の著作・翻訳2冊--ヴィンフリート ネルディンガー著、清水光二訳『ナチス時代のバウハウス・モデルネ』(大学教育出版、2002年)、『ドイツ語コンパクト』(大学教育出版、2001年)。