
ホーム>学部・学科>アニメーション文化学部 アニメーション文化学科>教員インタビューアニメーション文化学部で美術・デッサンを学ぶということ

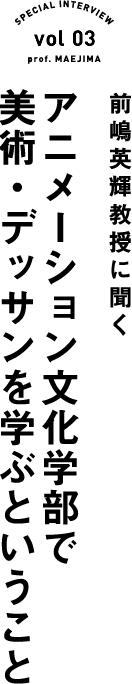
専攻:美学・美術史、美術教育。1993年岡山大学大学院教育学研究科美術教育修士課程修了。吉備国際大学文化財学部准教授を経て、2014年4月から現職。2008年、粘土場による教育で、日本美術教育学会 第四回実践研究奨励賞。2013年10月、一陽会 一陽展会員賞。彫刻家として活躍する一方、大量の粘土を活用して幼児が自由に遊び造形感覚を養うことができる「粘土場」の実践活動など、美術教育の実践・研究を行う。
 |
 |
| 前嶋英輝 カルクカスカナル音ニテ 182×52×46 FRP 1984 |
前嶋英輝 MODA 171×53×45 ブロンズ 1999 |
 |
 |
| 前嶋英輝 五六七を待つ 142×43×78 石膏 ガラス 2003 |
前嶋英輝 Sの頭像 25×21×26 石膏 2016 |


研究室の書棚の前で。美術書・哲学書に交じって、マンガ版『風の谷のナウシカ』も。
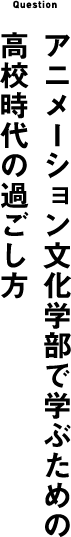


研究室のデスクにて。画面は、本シリーズ第1回井上先生のインタビュー。室内の緑が印象的。